ヘルプデスク業務は、ユーザーからの問い合わせ対応や問題解決において、企業にとって非常に重要な役割を担っています。特に社内ヘルプデスクは、自社の業務を効率的に進めていくうえで欠かせない存在です。
しかし、貢献度合いを定量的に示せなければ、「適切な人材評価ができない」「コストパフォーマンスを発揮できているのか分からない」と頭を抱えてしまう方も存在します。
そのようなときに大切な取り組みが、KPI(重要業績評価指標)やKGI(重要目標達成指標)を用いた「ヘルプデスク向けの目標設定」です。ヘルプデスク業務に適切な目標設定をすれば、効率化や品質の向上も期待できます
本記事では、具体例を通じて、顧客満足度を向上させるために設定したいヘルプデスク向け目標設定の具体例を詳しく解説します。特に、チーム全体の目標を明確にし、各メンバーの役割を理解させる方法についても触れています。これにより、サポート体制が強化され、お客様の期待に応えることが可能です。
ヘルプデスクの仕事と課題

「ヘルプデスク」とは、幅広い範囲のサポートを提供する部門を指します。
大きく分けて、「社外の顧客向け製品やサービスに対するカスタマーサポート業務」と、「社内の従業員からの製品やシステムの使い方、トラブルに関する問い合わせへの対応業務」の2種類が一般的な業務です。
一部の企業では「テクニカルサポート」と呼ばれ、カスタマーサポートと同じ窓口として運用されるケースもあります。本記事は、社内ヘルプデスクについて記述します。
ヘルプデスクの仕事
ヘルプデスクのなかでも、「社内ヘルプデスク」は企業や組織内の従業員が使用するIT環境の問題解決を担うのが役割です。技術的なサポート提供で、業務の効率化とスムーズな運営を支援します。
多岐にわたる業務内容が含まれ、IT関連の問題解決、システムのサポートなどが主な役割です。以下は社内ヘルプデスクの具体的な業務内容です。
- 問い合わせ対応:従業員からのITに関する質問や問題(PCの不具合やソフトウェアの使い方に関する質問)に対応
- 入退社の端末管理:入社する従業員に対して必要な機器やソフトウェアの準備、退社する従業員が使用していた端末の回収やデータの消去
- ウイルス対策とセキュリティソフトの管理:社内ネットワークや端末のセキュリティを維持するため、ウイルス対策ソフトウェアのインストールや更新の管理
ヘルプデスクによくある課題
社内ヘルプデスクによく見られる課題のひとつが、「業務が多岐にわたり担当者への負担が大きい」点が挙げられます。社内ヘルプデスクの仕事は、やりがいが大きい反面、業務が多岐にわたるため十分に人員が配置されていないと、1人ひとりに大きな負荷がかかります。
以下は社内ヘルプデスクが抱える課題の具体例です。
- 対応範囲の広さ:社内のIT環境やシステムが多岐にわたるため、全てに対応するのは非常に困難。特に、専門的な知識が必要な問題に対応するのが難しい
- 問題解決までの時間の長さ:複雑な問題やシステム全体に関わる問題になると、問題解決までに時間がかかり、従業員の業務が滞る可能性がある。また、問題が深刻化する前に迅速な対応が求められる
- 高いサポート要求と負荷:従業員からのサポート要求が集中する時間帯や、急なトラブルが発生した場合、負荷が非常に高くなる場合がある。特に大規模な企業では、日々多くの問い合わせに対応しなければならず、対応の遅れや品質が低下する恐れがある
ヘルプデスクで目標設定するメリット

定量的に評価を下せない状況では、どのようなポイントに課題があるのか把握しづらく、業務の改善方法に頭を悩ませてしまう方も少なくありません。
そこで、ヘルプデスクで目標設定を行えば、以下のようなメリットを得られます。
- 業務効率が上がる
- 対応の品質が上がる
- 適切な評価ができる
- 業務の属人化を防げる
業務効率が上がる
ヘルプデスクに目標数値を設定すれば、従業員は達成に向けて効率的に業務を進めるため、無駄な作業を削減できます。例えば、「1日あたりの対応件数」や「高優先度のトラブル解決時間を最短化」などを目標にすると、従業員は重要な業務を効率的に処理する意識を持ちます。
結果として、生産性の向上や働き方改革の改善につながるのがメリットです。業務効率を高める取り組みが進むことで、担当者ごとの負担を減らす効果も期待できます。
対応の品質が上がる
顧客満足度を数値化して目標設定すれば、ヘルプデスク担当者は顧客視点を持って業務に取り組むようになり、より高品質なサービスを提供できます。
例えば、「1件あたりの対応時間、問題解決までの時間、対応後の顧客満足度」などを目標に設定すると、従業員はどのレベルの対応が求められているかを理解し、一貫性を保って対応を行えます。
適切な評価ができる
明確な目標を設定すると成果を具体的に測定でき、ヘルプデスク業務の評価基準が透明になるため、フィードバックや評価も公平で効果的なものになります。
例えば、「対応時間の短縮」「解決率の向上」「顧客満足度の向上」などの具体的な目標数値を設定すると、評価基準が定まります。これにより、従業員は何を達成すべきかが明確になり、評価者も客観的な基準に基づいて評価を行えます。
具体的な目標設定により公平な評価が行われると、ヘルプデスク担当者からの不満も減り、モチベーションの向上につながるのもメリットです。
業務の属人化を防げる
属人化とは、特定の従業員に特定の業務や知識が依存する状態を指します。業務が属人化すると、その従業員が不在の際に業務の滞りや、そのほかの従業員が対応できない事態を引き起こすリスクがあります。
そこで、具体的な目標設定をチーム全体で共有し、個々の従業員が同じ方向に向かって業務を進めると、業務の属人化を防ぎやすくなるのがメリットです。目標設定を適切に行うと、業務が標準化され、チーム全体で業務を円滑に回す体制を構築できます。
問題が発生した際の対応手順や解決策が標準化され、チーム内の全員が同じプロセスに従うようになるのもポイントです。その結果、特定の従業員に依存せず、誰でも同じ方法でヘルプデスク対応を行えます。
目標設定の方法とは?

社内向けヘルプデスクにおける目標設定は、従業員の生産性向上と満足度向上に不可欠な要素です。効果的な目標設定を行うためには、「KGI(重要目標達成指標)」と「KPI(重要業績評価指標)」を適切に活用する必要があります。
KGI(重要目標達成指標)とは、社内向けヘルプデスクの最終的な目標達成度を測るための指標です。「従業員満足度」「生産性向上」「コスト削減」などが代表的な例として挙げられます。KGIは、ヘルプデスクが目指すべき方向性を示す羅針盤のような役割を果たします。
KPI(重要業績評価指標)とは、KGI達成に向けたプロセスを測るための指標です。 KGIを達成するために、どのような活動を、どのくらいのレベルで実行する必要があるのかを具体的に示すのがKPIとも言えます。
例えば、従業員満足度というKGIを達成するために、KPIとして「問い合わせ対応時間」「解決率」「顧客満足度」などを設定することが考えられます。
社内向けヘルプデスクにおける目標設定のステップは、以下のような流れで行うことが一般的です。
- KGI(重要目標達成指標)の設定
- KPI(重要業績評価指標)の設定
- KPIのモニタリング
- KGIの評価
1. KGI(重要目標達成指標)の設定
まず、ヘルプデスク全体の最終目標であるKGIを設定します。組織全体の目標や課題に基づいて、達成すべき目標を明確にしましょう。
- 社内アンケートでヘルプデスクに対する社内満足度90%以上を達成する
- 問い合わせ対応時間の短縮により、従業員の業務時間を平均10%削減する
- 問い合わせ対応件数を20%削減し、間接コストを削減する
2. KPI(重要業績評価指標)の設定
KGIを達成するために、どのような活動を、どのくらいのレベルで実行する必要があるのかを具体的に示すKPIを設定します。
- 従業員満足度向上
- 平均問い合わせ対応時間を5分以内にする
- 一回目の問い合わせで問題を解決する割合を80%以上にする(一次解決率を高める)
- 社内アンケートで4段階評価の3以上を獲得する割合を90%以上にする
- 生産性向上
- 1ヶ月あたりの問い合わせ対応件数を前月比10%削減する
- ヘルプデスクFAQサイトの利用率を向上させ、半年で自己解決率を30%以上にする
- コスト削減
- 電話問い合わせを減らし、チャット問い合わせの割合を50%以上にする
- 問い合わせ内容と対応履歴をデータベースに登録する割合を95%以上にする
3. KPIのモニタリング
設定したKPIの進捗状況を定期的にモニタリングし、必要があれば改善策を講じます。
- 毎月、各KPIの達成状況をグラフで可視化し、チーム全体で共有する
- KPI達成状況が芳しくない場合は原因を分析し、改善策を検討する
- 例)問い合わせ対応時間が長すぎる場合は、対応マニュアルを見直したり、FAQサイトを充実させたりする など
4. KGIの評価
KGIの達成状況を評価し、次期以降の目標設定に活かします。
- 半年ごと、または1年ごとにKGIの達成状況を評価する
- KGIが達成できなかった場合は、原因を分析し、次期以降の目標設定に反映させる
- 例)従業員満足度が目標に達しなかった場合は、問い合わせ対応品質を向上させるための研修を実施したり、ヘルプデスクの体制を見直したりする など
ヘルプデスクにおける目標設定の具体例

ヘルプデスクにおける目標設定では、業務の目的を理解したうえで、ビジョンに沿ったKPIの設定が必要です。ここでは、ヘルプデスク向け目標設定の具体例として、よくKPIに設定される以下のポイントを解説します。
- 問い合わせ件数
- 解決までにかかる時間
- 依頼した従業員の満足度
- 運用コスト
問い合わせ件数
社内からの問い合わせが多い状況は、製品やサービスの使い方がわかりにくい、または不具合が頻発していることを示唆している場合があります。そのため、問い合わせの数は少ない方が理想的です。
従業員が自己解決できる内容が増えると、問い合わせ対応にかかる時間が短縮され、サポート業務の効率化に繋がります。問い合わせ件数を減らす対策としては、「利用ガイド」「チュートリアルをわかりやすく提供」「よくある質問(FAQ)を充実させる」などが必要です。
解決までにかかる時間
解決までの時間が長いと、不満を抱かれるリスクが高いとされます。逆に解決時間が短いと、業務に与える影響が少なくなり、業務効率や生産性に直結します。
解決までのスピードを重視するあまり、応対品質が疎かにならないよう、ヘルプデスク担当者の教育機会の充実や直面した問題や解決方法を共有することが重要です。メンバー同士が経験を学び合い、同様の問題に遭遇したときに迅速に対応できるようになれば、解決時間の短縮に繋がります。
依頼した従業員の満足度
ヘルプデスク利用した従業員から満足度を測ると、サービスの改善や業務効率化などの目標設定が可能です。対応の速度や解決度、満足度や再利用意向などのアンケート調査等を実施すれば、ヘルプデスクの強みと課題を明確にできます。
例えば、説明のわかりやすさに関して不満が多ければ、トレーニングやマニュアルの改善が必要です。定期的にこのようなフィードバックを集め、改善点を具体的に施策として実行すると、従業員の満足度を継続的に向上できます。
運用コスト
現在利用しているサービスやツールが本当に必要か、また効率的な選択肢があるか見直しも重要です。現状の利用状況をしっかりと把握し、適切なツールを選定すると、コスト削減に繋がります。
またリモート対応を導入により現地での作業に依存することなく、物理的な移動や現地での作業に伴うコストを削減できます。
目標設定する際のポイント

目標設定を行う際には「SMARTの法則」を意識するとよいとされています。SMARTの法則とは、目標設定時に重要な下記5つのポイントの頭文字を取ったフレームワークです。
- Specific(具体的)
- Measurable(測定可能)
- Achievable(達成可能)
- Relevant(関連性がある)
- Time-bound(期限付き)
いずれかのポイントが欠けてしまうと、設定した目標が成果に結びつかず、効果的に活用できい恐れがあります。
以下は目標設定の具体例です。
悪い例:業務効率を改善する
→改善する具体的な方法や基準が不明確
良い例:ヘルプデスク対応の業務効率を3ヶ月以内に15%向上させる
→具体的な数値(15%)・期限(3ヶ月)・達成の方向性が示されており、進捗の測定が可能になる
悪い例:ヘルプデスクの問い合わせ件数を減らす
→具体的な達成基準がないため、進捗が測りにくい
良い例:問い合わせ件数を前月比で30%削減する
→時間軸(前月比)と具体的な数値(30%削減)を組み合わせると、達成に向けた行動計画が立てやすい
SMART基準を意識により、進捗を追跡しやすく、達成に向けた行動計画が立てやすくなります。
ヘルプデスクの業務効率化なら、アウトソーシングもご検討ください
目標設定は重要ですが、効果が現れるまでに時間がかかる場合があります。改善策の実行には、プロセスの見直しや従業員教育、ツール導入などが含まれるものの、根強く取り組むことで段階的に成果を上げられます。
とはいえ、「短期間での成果」を重視する方も少なくありません。そのようなときは、自社リソースを投入して対応力を高めるのではなく、ヘルプデスク対応のアウトソーシングを検討するのも有効な選択肢のひとつです。
私たちヘルプデスクパートナーは、オフィスの最適なインフラ構築から社内向けのヘルプデスク対応まで、お客様の業務が円滑に進むようサポートいたします。ネットワーク・サーバー・複合機・ビジネスフォンなど、グループ全体でさまざmな機器を取り扱っているため、幅広い範囲の対応が可能です。
情報システム部に専任スタッフを雇用する場合、給料・教育コスト・販管費など非常に高額な費用が発生します。私たちにお任せいただければ、雇用する場合の半分以下のコストで課題解決が可能です。
「ヘルプデスクパートナー」について、興味の湧いた方、詳しく知りたい方は気軽にお問い合わせください。


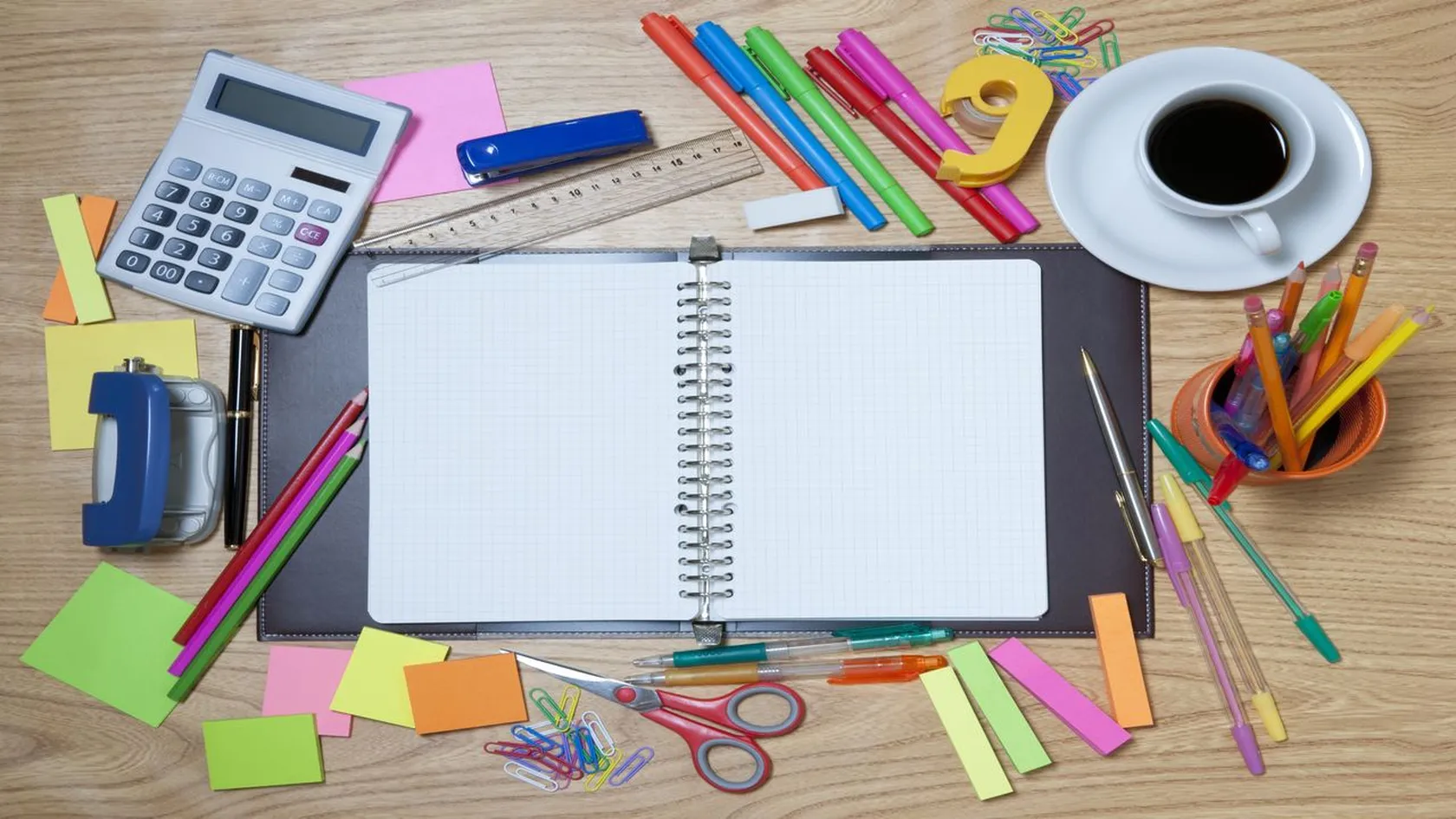
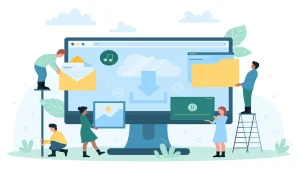





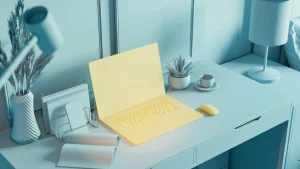

 10周年記念!初回限定キャンペーン
10周年記念!初回限定キャンペーン
