社内ヘルプデスクに寄せられる問い合わせの多くは、パソコンの操作方法やネットワークへの繋ぎ方など、定型的なものです。IT人材不足も深刻化しており、ヘルプデスク担当者の負担は増加している傾向にあります。
このような状況を打開するツールとして注目されているのが「チャットボット」の導入です。チャットボットは、よくある質問への自動応答などを通じて、ヘルプデスク業務の効率化やコスト削減に貢献します。
本記事では、社内ヘルプデスクにチャットボット導入が注目を集める理由について、チャットボットを導入するメリットや、チャットボット導入までの流れについて解説します。
社内チャットボット導入を成功させるためのコツについても解説しますので、ぜひご参照ください。
社内ヘルプデスク向けチャットボットが注目される理由

社内ヘルプデスク向けチャットボットとは、FAQ(よくある質問)などの情報をもとに、利用者の質問に24時間365日、自動で回答できるツールです。「AIヘルプデスクツール」とも呼ばれます。
近年、働き方の多様化やIT環境の複雑化に伴い、社内ヘルプデスクへの問い合わせが増加しています。特に、テレワークの導入やIT人材不足は、ヘルプデスクの業務負荷増大に拍車をかけているのが現状です。
このような状況を背景に、社内ヘルプデスク向けチャットボットが注目されています。
社内ヘルプデスクの現状と課題
社内ヘルプデスクは、PCやネットワークトラブルの解決、社内システムの操作説明など、業務を円滑に進めるための重要な役割を担っています。
しかし、近年ではDX推進やテレワークの拡大により問い合わせ件数が急増しており、2025年の崖とも言われるIT人材不足も相まって、社内ヘルプデスクの業務負荷が拡大しているのも事実です。
繰り返し発生する定型的な問い合わせに追われることも多いため、社内ヘルプデスクではFAQやマニュアルを用意するケースがほとんどです。
しかし、FAQやマニュアルがあっても、「情報が見つけにくい」「内容が古い」「使い勝手が悪い」と活用されない場合も。トラブル解決をヘルプデスクに依存されてしまう点は、多くの社内ヘルプデスクが抱える課題となります。
チャットボットの導入で実現できる解決策
ヘルプデスクにチャットボットを導入すれば、社内ヘルプデスクが抱えるさまざまな課題を解決できます。チャットボットは24時間365日稼働できるだけでなく、即時解答・問い合わせの自動処理を行えるのが特徴です。
そのため、チャットボットの導入によって、以下のような課題も解消できます。
- よくある問い合わせ対応の効率化:定型的な質問はチャットボットが自動で回答するため、担当者はより複雑な問題や専門的な業務に集中できます。
- ヘルプデスク担当者の負担軽減:自動応答により、問い合わせ対応に費やす時間を大幅に削減できます。
- 利用者側の自己解決促進:従業員は時間や場所を問わず、必要な情報をチャットボットから即座に得られます。また、FAQなどとは違って解決提案をしてくれるため、利用率が高まり、自己解決を促しやすくなります。
- コア業務に注力する時間の確保:ヘルプデスク担当者が定型業務から解放されるため、システムの改善提案や企画立案といった、より付加価値の高いコア業務に時間を充てられるようになります。
上記の結果として、ヘルプデスク全体の業務効率が向上し、人件費などのコスト削減にも繋がります。ヘルプデスク向けチャットツールによっては、問い合わせデータの収集なども行えるため、商品改善や顧客分析に応用することも可能です。
「問題解決の自動化」を実現できる
社内ヘルプデスクの課題解決には、利用者の自己解決を促す仕組みの整備が重要です。社内FAQの充実やアクセシビリティの向上をしても、「自己解決率が思ったよりも上がらなかった…」と頭を悩ませるヘルプデスク担当者も少なくありません。
そこで、チャットボットをヘルプデスクに導入すれば、「問題解決の窓口」を一本化して利用率向上&問題解決の自動化を実現できます。チャットボットはFAQやマニュアルに比べて使いやすく、直感的な操作で情報にアクセスできます。
また、何が原因か分からない「あやふやなギモン」の方向性を固めて誘導できる点も特徴のひとつ。FAQよりも利用者の自己解決を促進する効果が期待できるのも、ヘルプデスクにチャットボットが選ばれる理由のひとつと言えます。
社内ヘルプデスクにチャットボットを導入して得られるメリット

社内ヘルプデスクにチャットボットを導入すれば、業務効率が向上し、従業員の利便性も高まります。具体的に、社内ヘルプデスクへチャットボットを導入して得られるメリットは以下のとおりです。
- 業務を効率化できる
- コスト削減を実現できる
- 24時間365日の対応
- ナレッジの蓄積・管理が容易
業務を効率化できる
チャットボット導入による大きなメリットのひとつが業務効率化です。よくある質問(FAQ)や定型的な問い合わせに対してチャットボットが自動で対応するため、担当者はより複雑な問題解決や付加価値の高い業務に集中できます。
また、チャットボットをヘルプデスクに導入すれば、迅速な回答を提供できる点も魅力です。問い合わせへの即時対応が可能なため、従業員の待ち時間を削減し、利用者の満足度を向上させる効果も期待できます。
コスト削減を実現できる
人的リソースの最適化によるコスト削減も、ヘルプデスクへチャットボットを導入して得られるメリットです。チャットボットが単純作業を代行するため、ヘルプデスクに必要な人員数を最適化し、人件費や運用コスト削減に貢献します。
とくに、夜間や一部サービスローンチ時など、スポット対応が必要な場合でも追加コストの発生なく運用できる点は大きな魅力です。問い合わせが急増しても、チャットボットなら柔軟に対応できるため、追加の人員配置も不要となりコスト削減を実現できます。
24時間365日の対応
チャットボットは常時稼働しているため、深夜や休日のお問い合わせにも対応できるのは大きなメリットです。利用者はいつトラブルが発生しても、必要なときにいつでもサポートを受けられる安心が得られます。
ユーザー目線では利便性が向上するほか、簡単にチャットボットへ問い合わせできるため、心理的なハードルを飛び越えて気軽に問題を解決&生産性向上を実現できます。
ナレッジの蓄積・管理が容易
社内ヘルプデスクにチャットボットを活用すれば、情報の蓄積と活用を、ヘルプデスク業務と同時に行えます。問い合わせの内容や回答履歴を記録していくため、履歴自体が貴重なナレッジベースとして活用可能です。
蓄積されたデータを分析すれば、新たなFAQ作成やサービス改善、さらにはサービス全体の品質向上に役立てられます。
また、特定の担当者の経験や知識に依存しない仕組みを構築できるため、業務の属人化を防ぎ、担当者の退職や異動による影響を最小限に抑える効果も期待できます。
ヘルプデスク業務を効率化するチャットボットの活用例

チャットボットは単に質問に答えるだけでなく、ヘルプデスク業務をより高度に効率化するためのさまざまな機能を備えています。ヘルプデスク業務の効率化に、チャットボットをどのように活用するのか、具体的な方法をご紹介します。
問い合わせ分類からFAQ追加まで自動化
AI搭載型のチャットボットであれば、寄せられた問い合わせ内容を解析し、自動で適切なカテゴリに分類することが可能です。
さらに、分類結果や解決に至らなかった問い合わせのデータに基づき、新たに追加すべきFAQや更新が必要なFAQをシステムが提案する機能もあります。
FAQ管理者は提案された内容を承認・編集するだけで済むため、FAQメンテナンスの負担が軽減され、問い合わせトレンドに基づいた効果的なFAQ改善が実現できます。
問い合わせ対応を自動化
チャットボットのコアな役割として、FAQやナレッジベースから適切な回答を検索し、自動で提示できます。
単に回答を示すだけでなく、「質問内容に応じて確認事項の選択肢を提示」「関連する追加情報を提供」などにより、ユーザーの自己解決をより強力にサポートします。
自動対応で解決できない複雑な問題は、担当部署や担当者へスムーズに連携(エスカレーション)する機能も設定可能です。これにより、一次対応の自動化と適切な担当者への振り分けを両立し、業務効率化を実現します。
定型文メールの自動作成
問い合わせ対応後のフォローアップや、特定の手続きに関する案内など、定型的なメール作成業務もチャットボットで自動化できる場合があります。
問い合わせ内容や送信先の属性(部署など)に応じた定型文メールを自動生成し、テンプレートを利用して部分的にカスタマイズすることも可能です。
チャットボットでの対応完了後に、関連メールを自動で転送・送信するよう連携すれば、メール作成にかかる時間を削減して担当者の負担を軽減します。
対応優先順位の自動判定
問い合わせ件数が多いヘルプデスクでは、対応の優先順位付けも重要な課題です。AIを活用したチャットボットの中には、問い合わせ内容の緊急度や重要度を自動で判定し、優先度の高い順にリスト表示する機能を持つものがあります。
そのため、担当者は対応すべき問い合わせチケットを効率的に把握でき、対応漏れや遅延を防止できます。結果として、問い合わせ対応全体の効率化が進み、顧客満足度の向上にも繋がるのがポイントです。
ヘルプデスク担当者の育成を支援
チャットボットは、新人担当者の育成支援ツールとしても活用できます。過去の膨大な問い合わせ履歴や対応事例をAIが分析し、効果的な対応方法や注意点などをまとめた教育情報として提供することが可能です。
なかには、研修プログラムやOJTの教材として利用したり、チャットボット自体がメンターのように機能し、担当者からの質問に回答したりアドバイスしたりする機能を搭載したツールも。
これにより、担当者の早期スキルアップを支援し、育成期間の短縮を実現します。
ユーザーサポートの品質向上
チャットボットによる24時間365日の迅速な対応、充実したFAQによる自己解決の促進は、ヘルプデスクにおけるユーザーサポート全体の品質向上に直結します。
ほかにも、「多言語対応機能」「チャット以外の多様なチャネル(メール、電話連携など)」に対応できるチャットボットを導入すれば、より幅広いユーザーニーズに応えることが可能です。
さらに、蓄積された問い合わせ履歴データを分析し、対応品質のボトルネックとなっている箇所を特定したり、FAQコンテンツを継続的に改善したりすることで、サポート品質を向上できます。
チャットボットの構築・導入までの流れ

ヘルプデスクにチャットボットを導入するには、準備・検証に工数がかかります。正答率向上のため、学習リソース収集やチューニングは欠かせません。
具体的に、ヘルプデスク向けにチャットボットを構築して導入するまでの流れをご紹介します。
- ヒアリング: 導入目的(解決したい課題)、設置場所(社内ポータル、グループウェアなど)、利用するFAQデータ、テスト導入の範囲などを明確にします。
- 設定・カスタマイズ: ヒアリング内容に基づき、企業のニーズに合わせてチャットボットのデザインや応答シナリオなどを設定・カスタマイズします。
- FAQデータ収集・整理: チャットボットが回答の根拠とするFAQデータを収集し、精度向上のために内容を整理・精査します。
- 応答フロー構築: 自動応答で完結するシナリオ、有人対応へ引き継ぐ場合のフローなどを設計・設定します。
- テスト運用(PoC)・チューニング: 一部の部署や担当者でテスト運用(Proof of Concept)を行い、応答精度や使い勝手を確認します。発見された課題に基づき、FAQデータやシナリオを修正・調整(チューニング)します。
- 納品・運用開始: テスト運用とチューニングを経て、本格的な運用を開始するための準備(本番環境への設置、利用者への告知など)を行います。
- 管理者向けレクチャー: チャットボットの管理画面操作や、FAQのメンテナンス方法などについて、担当者向けのレクチャーを実施します。
- 有人対応ルール整備: チャットボットから有人対応へ引き継ぐ際のルールや連携方法を明確に定めます。
- メンテナンス・改善: 運用開始後も、利用状況データ(質問内容、解決率など)を定期的に分析し、課題を抽出します。分析結果に基づき、FAQの追加・修正や応答シナリオの改善を継続的に行い、回答精度を維持・向上させます。
社内向けであれば問題ありませんが、AIチャットボットをヘルプデスクに使う場合は機密情報の取り扱いに注意する必要があります。学習データに機密情報が含まれていると、意図せずAIがそれを学習し、外部に漏洩してしまうリスクも。
ChatGPTなど一部のサービスでは、入力データを学習させない設定や法人向けプランが提供されているため、確認が必要です。また、近年注目されているAIヘルプデスクツールの「FAQチャットボット」などを利用すれば、特定のFAQを元にチャットを返答できるため、想定外な動作が起こりにくくなります。
自社でチャットボットを構築するのが難しい場合は、既存のAIヘルプデスクツールを利用するのも選択肢のひとつです。
社内チャットボット導入を成功させるための3つのコツ

チャットボットの導入を成功させるためには、導入前の準備から運用までしっかりとした計画が必要です。ここでは、社内ヘルプデスク向けにチャットボットを採用するうえで、導入効果を最大化するコツについて紹介します。
明確な目標設定を行う
チャットボット導入にあたり、最初のステップとして重要なのは、適用範囲を明確にすることです。すべてのヘルプデスク業務にチャットボットを適用させるのは現実的ではありません。
まずは、自動化したい業務範囲を絞り込み、必要なデータの整備から始めましょう。たとえば、「問い合わせ頻度の高い定型的な質問は何か?」などを絞り込み、必要なデータを用意する取り組みが重要です。
導入後も対応履歴などを分析し、「回答内容を随時修正」「新たなFAQを追加」といった対応を通してチャットボットを継続的に改善し、「育てていく」視点が成功の鍵となります。
データ整理を入念に行う
チャットボットの回答精度は、学習させるFAQデータの質に大きく左右されます。しかし、考えうるすべてのQ&Aデータを登録のは非常に困難であり、効果的でもありません。
そこで重要になるのが、優先度の高い「よくある質問」の内容を精査し、社内の問い合わせ履歴などを参考にしながら、チャットボットに登録すべきデータを厳選する作業です。
導入前には、選定したデータの回答内容が正確か、分かりやすいかなどを精査し、必要に応じてチューニングを行うなど、検証作業に一定の工数がかかることを念頭に置いておく必要があります。
リリースまでの検証でユーザー体験を重視
チャットボットを本格的に運用開始する前に、十分な検証期間を設けることが大切です。
実際にヘルプデスクを利用する従業員にテストユーザーとして参加してもらい、「操作はしやすいか」「回答は分かりやすいか」「スムーズに問題解決に至れるか」といったユーザー体験(UX)に関するフィードバックを得ながら改善を重ねていきましょう。
検証が不十分なままチャットボットをリリースしてしまうと、「質問しても解決しない」「使いにくい」 という印象を与えてしまい、ユーザーの期待を大きく裏切る可能性も。
そうすると、せっかく導入したチャットボットが社内ヘルプデスクとして定着せず、導入コストだけがかさんでしまうリスクも発生します。
「チャットボットを使えばトラブルを解決できる」という成功体験を植え付けて、安定して利用してもらえる環境を構築することがチャットボット導入におけるもっとも重要なポイントです。
ヘルプデスク業務自体の効率化なら外注も検討を
ヘルプデスクにFAQ/AIチャットボットを導入すれば、定型的な問い合わせ対応を自動化し、業務効率化を実現できます。
しかし、チャットボットで自動化できるのは、主に単純な問い合わせに対する一次対応であり、ヘルプデスク担当者が「コア業務へ注力できる余力」を生み出すに留まるケースも少なくありません。
難易度の高い問い合わせ対応は依然として担当者のスキルに依存しており、情報システム部門などでは、PCのキッティングやアカウント管理といった、チャットボットでは対応できない物理的な作業も多く存在します。
そのため、ヘルプデスク業務全体が負担となっている場合、チャットボット導入だけでは本質的な解決に至らない可能性があります。
AIヘルプデスクツールなどを利用してチャットボットを導入するのも手ですが、本質的な問題解決なら「ヘルプデスク」のアウトソーシングがおすすめです。
リップルのヘルプデスクサービスである「ヘルプデスクパートナー」では、年間対応件数17万件以上、これまで100万件以上の対応で培った解決力に特化したノウハウがありますので、ネットワーク、サーバー、複合機やビジネスフォンなど、特定の部門だけに限らず、多様な問題や困りごとへのサポートが可能です。
「チャットボット」にはできない専門性の高い質問も、経験豊富なプロのスタッフによる対応が可能です。
ヘルプデスク業務のアウトソーシングサービス「ヘルプデスクパートナー」について、興味の湧いた方、詳しく知りたいという方は、お気軽にお問い合わせください。
記事を最後までお読みいただき、ありがとうございます。皆様のビジネスに少しでもお役に立てれば幸いです。







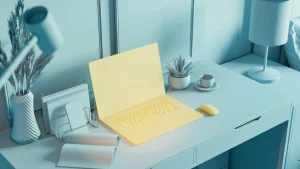



 10周年記念!初回限定キャンペーン
10周年記念!初回限定キャンペーン
